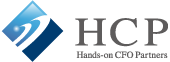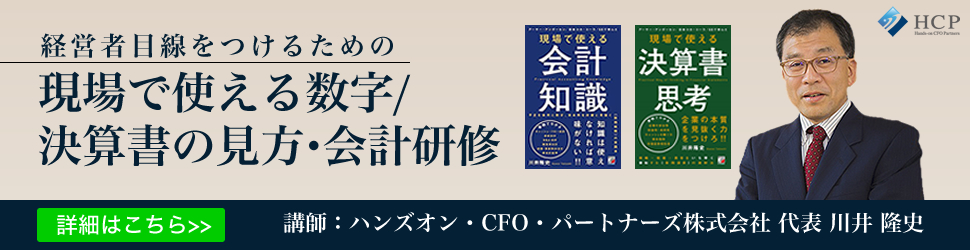数字で読み解くーUSスチール買収は高すぎるのか?
2025.06.25

目次
1.日本製鉄による米USスチール買収、約2兆円
2025年6月18日、日本製鉄がアメリカの老舗鉄鋼メーカー USスチール(U.S. Steel)を約2兆円(約141~142億ドル)で買収が完了したというニュースが発表されました。どちらかというとこれに関しては米国政府の重要な経営判断(工場閉鎖・生産縮小・雇用削減・本社移転など)に対して拒否権を持つ黄金株が話題となりましたがここでは主としてUSスチールの財務的な側面でこの買収を見ていきたいと思います。主なポイントは以下です
- 「すでに業績が悪化している企業では?」
- 「巨額すぎないか?」
- 「財務は本当に健全なのか?」
これらの疑問に答えるために、USスチールの2024年の最新決算(10-K報告書)をもとに財務面から冷静に分析してみます。
2. 財務の安定性と経営成績について
まずはUSスチールの2024年12月期のバランスシートから、主要な数値を確認します。
|
指標 |
数値(2024年末) |
|
総資産(Total Assets) |
$20,235 million |
|
総負債(Total Debt) |
$8,795 million |
|
株主資本(Stockholders’ Equity) |
$11,347 million |
|
現金および同等物 |
$1,367 million |
|
有利子負債 |
$4,252 million |
Debt/Equity比率:約0.37倍
資本に対して有利子負債は多いわけではなく財務的には手堅い印象があります。重厚長大の製造業では1.0倍を超える企業も珍しくない中、この水準はまずまず良好といえます。
一方で、損益計算書を見れば、収益力には大きな陰りが見られます。
|
年度 |
売上高($M) |
営業利益($M) |
純利益($M) |
EBITDA(調整後)($M) |
|
2022 |
21,065 |
4,170 |
2,524 |
4,290 |
|
2023 |
18,053 |
2,329 |
895 |
2,139 |
|
2024 |
15,640 |
705 |
384 |
1,366 |
利益は3年連続で縮小、売上は3年で約25%減少
- 営業利益は80%以上減少
- 純利益は大幅に減少
- USスチールの本業は明確に苦戦しており経営成績的にはかなりじり貧といえます。
そして、 稼ぐ力に対する借金の重さ(Debt/EBITDA)です
- 有利子負債:$4,252 million
- Adjusted EBITDA:$1,321 million
➡ Debt/EBITDA ≒ 3.21倍
稼ぐ力が落ちてきているのでやや心配で数値は良好とまでは言えませんが、借金が返せなくて大変といったレベルではないといえます。かなりじり貧な状態、しかし意外に財務状態は良好、下げ止まれば会社の維持自体は可能とは言えます。
3.今回の買収は高値か?
さて、それでは今回の買収は愚かな高値づかみなのでしょうか?
今回の買収価額が142億ドルとすると現状のUS StealのEBITDA1,321millionの約10.7倍、しかも現在どんどんと業績が下降しているので高値という見方はあるかもしれません。加えて、これは新聞記事などでも強調されていますがアメリカ政府、特にトランプ大統領の「介入」が要注意でしょう。
アメリカ政府の黄金株保有により黄金株により、以下のような行為には拒否権が行使されます:
- 米国内の製鉄所閉鎖
- 米国での生産撤退
- 技術の国外移転
つまり、「買収はできるが、完全な自由経営ではない」という制限付きの支配権となるのです。
当然日本製鉄側も高めづかみではないかという点は十分検討したと想像します。日本製鉄のDEレシオも買収直後は0.9程度となり財務的にも悪化はします。それでも日本製鉄が2兆円を投じる理由は以下と考えられるでしょう。
★戦略的な「電炉」強化と脱炭素対応
- USスチールは既に電炉(環境負荷の少ない製鋼法)比率が比較的高い(注:ただし売上ベーでは15%程度です)
- 日本製鉄の脱炭素戦略との親和性が高い
★米国の「製造回帰」に乗る
- IRA(インフレ抑制法)により、米国製造業に巨額補助金と税優遇
- 自動車、建設、インフラ向けの鉄鋼需要は今後も堅調
★グローバル供給網の確立
- 日本・欧州・米国の三極体制の確立
- 中国依存リスクを減らすグローバルな布石
この買収日本製鉄のグローバル戦略に基づくものであり、「今後どうするか」といったPMI(買収後統合)は、スピード感をもって、かつトランプ大統領の逆鱗に触れずに完遂するというなかなか難易度の高いものといえます。高値づかみかどうかは、ある意味経営手腕次第といえ、今後の動向興味深い案件といえますね。