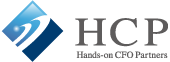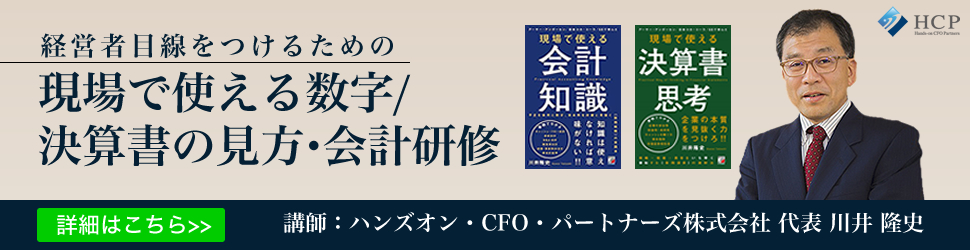雑な数値管理が組織を蝕む——トランプ関税から読み解く「納得感のない指標」の末路
2025.04.16

目次
1.トランプ関税が示した“雑な計算”の怖さ
数字で語ることが求められるビジネスの世界において、「数値管理」は最も重要な経営の土台のひとつです。しかし、その数値が「雑」である場合、どうなるでしょうか。形式上は正しくても、現場にとっては意味をなさない。そんな“ズレた”数値管理が、結果的に現場の疲弊や非効率を生むのです。
象徴的な例として、非常にイメージがわきやすいトランプ政権下の「関税政策」に触れてみましょう。
トランプ大統領が主張した「相互関税(reciprocal tariff)」は、米国が他国に対して一方的に赤字を抱えている状況を是正するために導入を目指した政策です。
この相互関税を達成するための追加関税率は以下のような数式で決められます:
追加関税率 ≒(米国の対某国貿易赤字 ÷ 米国のその国からの輸入額)× 定数
定数は、価格上昇が輸入量をどれだけ減らすか(貿易弾力性)と、関税が価格にどれだけ転嫁されるか(パススルー率)を組み合わせて設定されます。
ト ランプ政権はパススルー率を一律0.25と仮定していますが、これは実際の調査や産業別の実態とは異なりデータの出所が怪しく過小評価であると経済学者からは言われています。肌感覚的にも関税が20%上がってもその価格への転嫁は5%しかないというのは変です。その他突っ込みどころは満載なのですが本論とは離れるので省略します。
第一次トランプ関税などでも短期間で対策を強いられ、結果的に“迂回輸出”などの姑息な対応策が横行しました。
このように、雑な数値ロジックは、現場に不合理なプレッシャーだけを残すのです。
2.米系企業で経験した「雑な数値目標設定」
実はこうした雑さは、アメリカの一部グローバル企業の中でも見られる傾向です。
私が過去に勤務していた米系の大手企業では、本社から「構造改革」と称して現地法人に人員削減の指令が下されたことがありました。
その際に使われた基準は(多少調整計算はあるものの結局は)「売上高に対する適正人員数」。このロジックで部門ごとに“あるべき人員数”が割り当てられ、それを超える人数は削減対象とされました。一見、合理的に見えるかもしれませんが、実態はまるで現場を知らない机上の空論でした。
たとえば、ある国の法人は売上規模こそ小さいものの、高マージンのコンサル型ビジネスに特化していたり、逆に他の国は大量取引の薄利多売モデルだったりします。当然、必要な人員構成も大きく異なります。組織も国によって異なりその定義も異なります。
さらに、例えばマーケティングの適正人員数はX人のようなことを言われた際、「営業企画部」は営業とマーケティングの中間的な機能を持っていましたが、どちらの部門にカウントすべきかという“神学論争”が発生。現場では混乱が広がりました。
結果的にどうなったかというと・・・「目標達成」でも現場はボロボロに
最終的に数字上は「目標達成」とされ、本社の担当者も現地法人のマネジメントも表向きには満足していました。しかし、実態は違います。
削減した人数分を補うために、外注化を短期間で無理に活用した結果、コストはむしろ上昇。また、業務の押し付け合いが部門間で発生し、社内の雰囲気も殺伐としたものに。つまり、「目標数値は表面的達成されたが、コストは減らず、組織は弱体化した」状態になってしまったのです。
3.雑な数値管理がもたらす「ブルシットジョブ化」
雑な数値管理の最大の問題は、執行者のモチベーションを著しく下げる点にあります。
・計算の根拠が納得できない
・目標が短期間かつ非現実的
・そもそも達成しても意味がないように感じる
こうした目標を与えられると、現場は「やらされ感」に満ち、「ブルシットジョブ(無意味な仕事)」としてしか受け止められなくなります。この結果、本来生産的であるはずの仕事が、「数字合わせのためだけの仕事」に変質してしまうのです。
数値管理において、すべてを完璧に精緻に計算する必要はありません。しかし、「ロジックに筋が通っており、納得できる」ことが最も重要です。
現場が理解し、共感できるロジックであれば、たとえ達成が困難であっても、自発的な工夫や改善が生まれます。そして、達成までの時間軸も現実的でなければなりません。
逆に、雑で納得感のない数値管理は、組織の信頼と活力を確実に削いでいきます。政治にせよ企業経営にせよ、「数値の扱い方」は、その組織の姿勢を如実に映し出します。
表面的な数字だけを追い求めるのではなく、「なぜこの数値が必要なのか」を丁寧に説明できることが、経営者やマネジメントの重要な責任だと感じています。
目先の数字に飛びつく前に、その“計算ロジック”を、今一度問い直してみませんか?