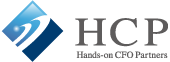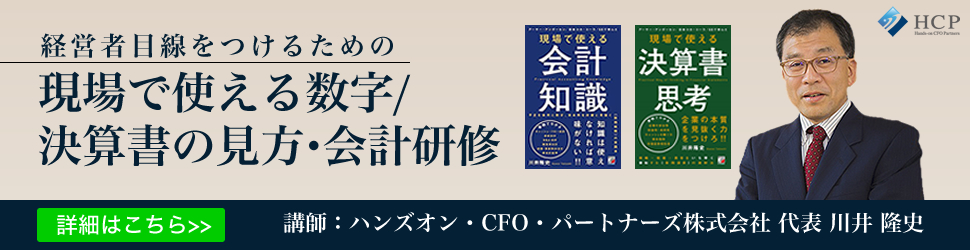オルツ不正会計事件に思うこと――監査法人が“見逃した”決定的な盲点
2025.08.22

目次
1.オルツ不正の規模と衝撃
AIスタートアップのオルツにおける不正会計は、ほとんど不正に計上した売上と利益で上場したという衝撃的なものでした。第三者委員会の調査報告書によれば、2020年12月期から2024年12月期の約4年間にわたり、売上高・広告宣伝費・研究開発費などで累計約119億円の不正計上が認定されています。
特に売上高では、ある年度において「最大で公表された売上の91%以上」が不正によるものだったと報じられています。つまり、外部に示されていた業績の大半が虚構だったということです。これは企業経営の実態を根底から覆す規模であり、投資家・取引先・従業員に与える影響も極めて深刻です。
この数字を見ただけで、多くの方が「どうしてこんな巨額の不正を誰も気づかなかったのか」と疑問を抱かれるのではないでしょうか。
2.オルツ不正スキームの概要となぜ発見できなかったか
第三者委員会の報告書を非常にざっくりとまとめると、オルツの不正会計は以下のような手口で行われていました。
- 循環取引(SPスキーム)
特定の関連会社や取引先を介し、実態のない売上を計上した。 - 広告宣伝費・研究開発費での資金の循環
広告宣伝費や研究開発費の一部を不正に計上し、事態のない売上に対して資金を還流させた
こうした取引は複数の会社を経由し、契約書・請求書といった形式的な証憑を揃えることで、一見すると正規の取引に見えるように作られていました。
不正の規模と巧妙さは確かなのですが、「監査法人はなぜ見抜けなかったのか」という問いが当然出てきます。委員会の指摘や私自身の経験を踏まえると、主に次の要因が挙げられます。
- 取引の複雑化による検知困難性
関連会社を経由させた循環取引は、証憑だけを見ると正当な売上に見える。資金の流れも一時的に実在するため、形式的な監査手続きでは発見が難しかった。 - 監査法人の検証不足
前任監査人から循環取引の可能性を示唆されていたにもかかわらず、後任監査人は十分な追加検証を行わなかった。この「警告の軽視」が被害拡大につながった。 - 形式主義に陥った監査
現在の監査現場では金融庁や監査基準の要求によりチェックリストが膨大になり、形式的な確認に追われがちになる。その結果、「何かおかしい」という感覚を深掘りする余裕が失われている。
つまり、複雑化した不正スキームと、形式偏重の監査環境が相まって、発見が著しく困難になったのではないかというのが私の意見です。
3.私の見方 ― リスクと監査のあり方
ここからは、特に私自身の私見を率直に述べたいと思います。ある有名な大学教授が「リスクのある会社は大手監査法人が受託すべき」と語っていました。しかし実際には、上場準備企業などリスクの高い会社ほど、大手監査法人は受託を避ける傾向があります。規則やリスク管理の観点からすれば理解できる面もあります。ただ、イノベーティブな会社は必然的にリスクが高い側面をもっています。その結果「こじんまりとしたお行儀の良い会社」しか上場できない環境を生んでいるのではないかと懸念しています。
一方で、不正が発覚するたびに金融庁のご指導の下、監査チェック項目は増え、現場の監査人はますます形式に縛られます。どんなに形式的だなと感じていてもやっていないと後日の検査でチェック漏れがあると指摘事項となり膨大な疎明資料を作成、最悪業務停止や禁止になります。したがって、監査人はデータの山に追われて会議室にこもってひたすらパソコンにインプットするだけのマシーンになっています。
しかし本当に大切なのは、昔から言われてきた「違和感を追う姿勢」ではないでしょうか?監査用語でいえば「健全なる懐疑心」です。古い監査人のたわごとと言われるかもしれませんが、私が若手の頃は「何かおかしいと思ったら徹底的に掘り下げろ」と指導されました。結構クライアントの現場にもいって何か腑に落ちないようなことがないか感覚的なものも大切にしていました。書類が揃っていても何か不自然さがあれば、その感覚を大切にする。そうした実質重視の姿勢こそが、不正を防ぐ最大の武器になるはずです。
AIによる不正検知が話題になっていますが、最終的には人間の「変だな」という感覚と掘り下げる執念がなければ、不正は見抜けません。良いシナリオとしては形式的な部分はAIが担い、人間はおかしいなと思ったところを掘り下げるそんな監査になるといいのですが・・・。
オルツの不正は、119億円という桁外れの規模でした。これを単に「高リスクな会社と悪質な経営者の問題」とそれに対する「監査のチェック不足」と片付けてしまえば、また同じことが繰り返されます。必要なのは、形式的な監査強化ではなく、実質を見抜く力を取り戻すこと。そして「リスクがあるから排除する」のではなく、「リスクがあるからこそ監査の目をじっくり入れる」仕組みづくりです。
日本の資本市場が健全に発展していくためには、形式に縛られすぎず、違和感を大切にする監査姿勢と、ユニークな企業が正当に評価される環境の両立が欠かせないと思うのです。