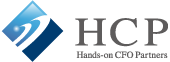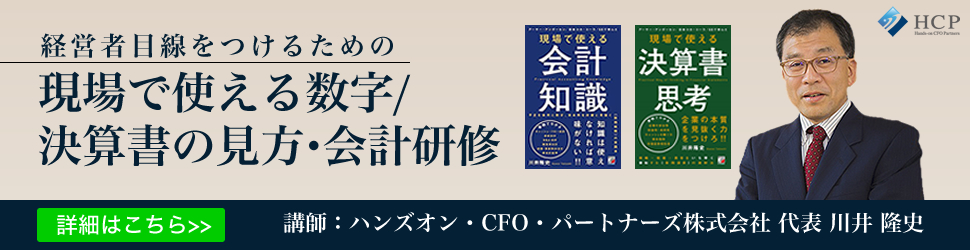ROIC経営の光と影――オムロンの事例から学ぶ「効率」と「成長」の両立
2025.09.19

目次
1.効率経営の優等生が直面した試練
「ROIC経営の優等生」と呼ばれてきたオムロン。ROIC(投下資本利益率)を分解して現場レベルまで浸透させた「逆ROICツリー経営」は、国内外の経営書でも取り上げられるほど高い評価を受けてきましたし、私も個人的に尊敬の目で見てきました。
しかし最近のニュースでは様子が違います。2025年3月期の決算を見ると、売上高は約8,018億円(前年比▲2.1%)、ROICはわずか2.1%(前期1.1%)と、かつて10%を超えていた水準から大きく低下しました。
2026年3月期第一四半期を見ても前期と営業利益はほぼ横ばい、残念ながら再浮上の明らかな兆しは見えていません。「効率の象徴」だったはずの仕組みが、逆に成長投資やイノベーションを抑え込んでしまったのではないのか?という疑問が沸き上がります。 なぜオムロンはつまずいたのか?ということに関していろいろと会社の開示資料や経済誌などで言われていることを私見も交えてまとめると以下になるでしょう。
外部要因
- 制御機器事業(FA部門)の不振:売上の半分を占める主力部門が、2023年度に中国市場の需要急減を受け、売上は前年度比▲19.0%、営業利益は▲75.0%と大幅減。2024年度も営業利益は少し回復したものの売上の低下状況は変わっていません
- 半導体・EV依存の影響:大口顧客が集中していた分野で需要が急速に冷え込み、市況変動をもろに受けました。
内部要因
- 在庫管理の失敗(2023年度):制御機器部門で在庫が一時的に通常の約2倍に膨張。売上予測が過去データに依存していたため需要減を見誤り、在庫滞留を招いたとされています。
- 過去データ依存の予測手法:会社自身も「予測が過去の経験値に基づいていた」と説明しており、結果的にROICや成長率の“過去の高さ”を信じ込んでしまったといえるかもしれません。
- 成熟市場偏重の投資判断:開示資料からは明確に確認できませんが利益が出やすい成熟市場への投資が優先され、ポートフォリオ硬直化を招いた可能性があります。
ROICは確かに「効率」を徹底させましたが、その一方で「長期投資が後回しになる」傾向もあります。研究開発や人材育成は短期的にROICを押し下げるため、現場が躊躇してしまう。これは多くの企業が陥りがちな“効率経営の落とし穴”です。
2.突破口の「二本立て」体制
オムロンも優れた企業ですので一般的に言われている落とし穴を認識していないわけではありません。この課題に対処するために、2018年にイノベーション推進本部(IXI)を設立し、「社内スタートアップ型」の仕組みを導入。介護予防サービスや新規データソリューションなどを生み出してきました。
さらに2023年にはデータソリューション事業本部(DSB)を立ち上げ、IXIが蒔いた種をスケールさせて収益化する体制に。
つまり、
- IXI=「新規事業の種まき」
- DSB=「育成と収益化」
という役割分担を敷き、効率経営の枠を超える仕組みづくりを進めています。
もっとも、DSBについては「十分に成果を出せていないのでは」という懸念はあります。ROIC基準で評価すると、新規事業はどうしても優先順位が下がります。初期投資が大きく、利益化まで時間がかかるからです。結果として、挑戦的な案件ほど投資判断が鈍りがちになる、これは特にDBSでシビアにROICで評価された際に起こりうるのではないかと思います。
加えて、IXIで芽が出ても、DSBに移管された段階で「効率経営」の仕組みに組み込まれてしまい、スピード感や柔軟性が薄れてしまうのではないか――。私はそのように感じています。特に事実を確認できたわけではありませんが、仕組み上そうしたリスクは十分考えられます。
まとめるとROIC=効率の物差し、DSB=長期投資と育成が必要この2つは本質的に緊張関係にあり、今のところオムロンは完全な解を見つけられていないように見えます。
3.オムロンのケースからの学びとは
オムロンの事例から見える教訓はシンプルかもしれません。しかし、現実かなりの経営力が必要でしょう。言うは易く行うは難しです。
- 効率と柔軟性の両立
ROICは羅針盤として有効。ただし、市場変化に即応できる“柔軟性”を持つことが欠かせない。 - 長期投資の覚悟
短期ROIC低下を恐れず、人材・研究開発・ブランドへの投資を戦略的に続けること。 - 文化の両輪
「効率」を重視する事業部門と、「挑戦」を後押しする新規事業部門を並走させること。
ROIC経営は「効率の教科書」でした。しかし、オムロンの例はそれだけでは未来を切り開けないことを示しています。言い換えれば「効率だけでは会社は伸びない。成長のための“余白”が必要なのかもしれません。あなたの会社ではどうでしょうか?効率の名のもとに未来の芽を摘んでしまっていないでしょうか?