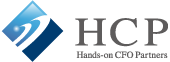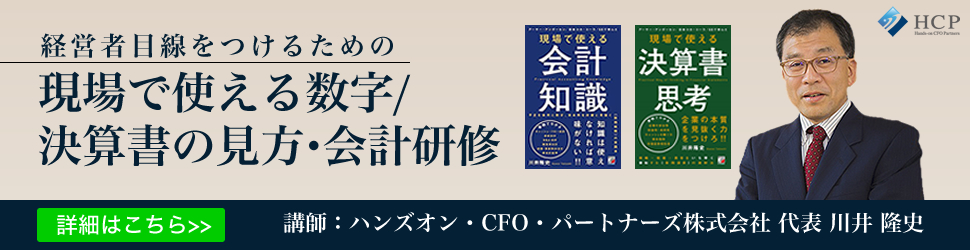“公立小学校型教育・研修”の限界ーできる社員が辞める会社辞めない会社
2025.11.04

目次
1.「期待の社員」が会社を去る
人材の流動化が進むなかで、「優秀な社員ほど辞めていく」という声を経営者や人事部門からよく耳にします。新入社員の3割、中途社員の5割が3年以内に離職する——そんなデータもありますが、問題は単なる3割・5割といった数字ではありません。
「辞められると困る社員」が辞めることで、組織の競争力が確実に低下していくのです。
しかも、特に「辞められると困る社員」の退職は必ずしも「給与不満」や「上司との関係」では説明できないケースが増えています。
ヒアリングをしてみると、彼らの言葉は意外にシンプルです。「ホワイトすぎてゆるすぎる、したがってここにいても、自分の成長が感じられない。」つまり、「働く意義=学びの実感」が持てなくなったとき、「辞められると困る社員」は会社を去るのです。
2. 社員教育が“公立小学校型”になっていないか
昭和の日本企業では、上司の指示に従い、ハードワークをこなす社員が“できる人”でした。しかし、令和の時代に成果を出すのは「自律的に考え、周囲を巻き込めるタイプ」です。彼らは忠誠心よりも「成長機会」を重視します。だからこそ、学びの設計が浅い企業ほど、優秀層が離れていくといえます。
多くの企業は社員教育として E-learning や 階層別研修 は整備しています。制度としては立派でも、実際の効果には限界があるのではないでしょうか。
・E-learningは「いつでもできる」=「結局やらない」。
・階層別研修は“全員平均”向けで、優秀な上位層には物足りない。
この構造、まるで「全員が同じ授業を受ける公立小学校」と同じです。優秀な生徒にとっては簡単すぎ、刺激がない。結果、学ぶ意欲を失っていきます。
人事の研修担当者は「理解できなかった」「ついていけなかった」といった研修のアンケート結果を恐れます。私も企業研修を行う講師として反省点ですが、やはり落ちこぼれを出さないことに眼が向きがちです。優秀層には「そこそこの満足」しか与えていない可能性は大いにあります。リピートを取るために、アンケートの5段階で3(普通)以下は絶対出さないことを目指すとそうなりがちです。
一方で、優秀な彼らが求めているのは、「進学塾型」の学びではないでしょうか。つまり、「できる人をさらに伸ばす」ための集中育成プログラムです。私は以前、欧米系企業に在籍していた際、この「進学塾型教育」が制度化されているのを見ました。社内の人材を“能力×成果”の2軸でプロットし、右上(ハイパフォーマー)に位置する社員には、超一流の外部講師による特別研修が提供され、費用も時間も惜しみません。
上司もその社員が学ぶ時間を確保するため、部下の研修参加には積極的に協力する。間違っても「この忙しいのに研修?」などとは発言しません。それが「人を育てるマネジメント」だと理解されています。手前味噌ですが私も米国企業の米国研修センターやその他海外での一流講師による研修を受講させていただき、上司もうまく仕事を調整、協力してくれたことは本当に今でも感謝しています。
一方、多くの日本企業ではどうでしょうか。「できる人に仕事が集中する」のが現実です。「忙しくて研修なんて出てられない」、学ぶどころか、忙しさの中で燃え尽き、やがて転職サイトに登録されてしまう。これは、教育の“設計ミス”です。
3.人を「辞めさせない」のではなく「伸ばす」
辞められると困る社員を引き留めるために必要なのは、給与でも福利厚生でもありません。「成長実感を与える仕組み」です。ここに経営層が注力すべき3つのポイントがあります。
① 優秀層への教育投資を“傾斜配分”する
「平等」ではなく「最適配分」。意欲と実力のある社員には、専門性の高い講師やプロジェクト機会を優先的に与える。
一律研修を全く否定するものではないですが、ハイパフォーマー向けの少人数制・討議型プログラムをもっと充実させるべきでしょう。
② 学びの時間を“業務の一部”に組み込む
「研修に行かせる時間がない」は言い訳です。上司の評価項目に“部下を学ばせる姿勢”を入れるだけでも、文化は変わります。業務配分の中に「学習のための余白」を設けることが、長期的には生産性を高めます。
③ 成長サイクルを“制度”で回す
研修→挑戦→評価というサイクルを明確に制度化し、学んだ内容が昇進・評価に直結する仕組みをつくる。これにより、学びが“自己啓発”から“経営戦略”へと格上げされます。
「辞められると困る社員」は、いまや会社の“資産”です。この資産を維持・成長させる唯一の方法は、学びのデザインを経営課題として扱うことです。かつて「終身雇用」は“安定”の象徴でした。しかし今の時代、「辞められると困る社員」が会社に留まる理由は“安定”ではなく“成長”です。あなたの会社では、こういったできる人に「学ぶ時間」を与えていますか?それとも、できる人に「仕事だけ」を与えていませんか?